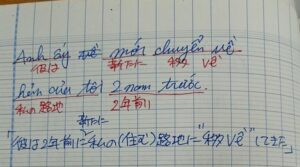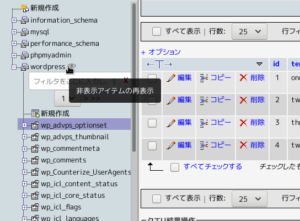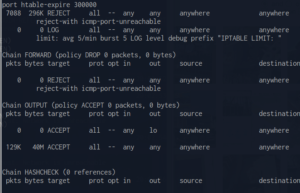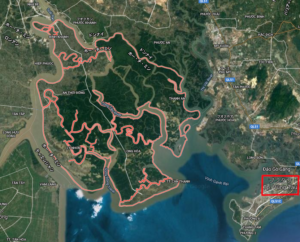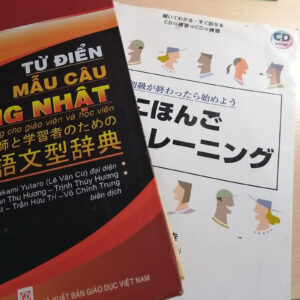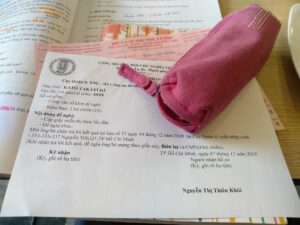2025年3月の読書記録
今月も子育てに大忙しであまり読めませんでした。ノンフィクション4冊・フィクション4冊・まんが9冊
ノンフィクション(4冊)
★★★★☆
📔 『教養としての俳句』青木亮人/NHK出版
なるほど、今の俳句は正岡子規が「かなり乱暴に打ち立てた」ものなのか。最近俳句本をよく読んでいるが、何が俳句で何が俳句でないかはわかってきた。ラズウェル細木の酒飲み漫画に毎回くっついている17文字の『俳句のような何か』がなぜ気持ち悪いのか、いまなら理屈で説明できる。あれはつまり、実際は「写生してないん」だな。その上、「どうしても使いたい言葉」に縛られてしまっている。だから「俳句のような何か」にしかなっていないんだなあ。
📔『「死にたい」 に現場で向き合う 自殺予防の最前線』/松本俊彦/日本評論社
★★★★☆
精神科医が「自殺する人の診察をしたときに感じる違和感」というのはよく聞くけど、これって「記憶を遡って改ざん」してるんじゃないだろうか?
📔『無戸籍の日本人』井戸まさえ/集英社文庫
★★★★★
今月は二重国籍のうちのムスメのパスポートを作ったりしたこともあり、「戸籍」「本人の証明」などに関して前々から気になっていたので購入して読んでみた。この本で主に取り上げられているのは「民法772条による父親の推定」というやつである。「婚姻中に生まれた子、もしくは離婚300日以内に生まれた子は、戸籍上の父親・離婚前の父親の子とする」という明治時代に作られた法律が放置されてきたことにより、DV夫と書類上の離婚ができずにいた女性などの新しい夫との子が、法律上前夫の父となってしまう、そしてそれを避けようとするとどうしても無戸籍になってしまうという大問題。当事者であり政治家でもある作者がこの法律と戦い、また無戸籍者のためのサポートをしてきた事が書かれている(なおこの法律および女性の再婚制限は2022年に法改正されている)。この中に登場する自民党の「保守的な」議員の「離婚とかいう不埒な行為を行ったのなら、子に類が及んでも当然だ。自業自得だ。『伝統的家族制度』を破壊しようとした罰だ」という考え方は本当に腹が立つし、彼らが『伝統的家族制度』とやらのために未だに政界で暗躍しまくっていることにゾッとする。また稲田朋美は本当に頭が悪いのだということもよくわかった。「どんなに熟慮して法律を作ったとしても、時代に連れ、人に連れ、思いがけない事件が起こる」という当たり前のことを忘れて「法律がそう言ってるならそうだろう」で済ませてしまう日本人には、やはり問題があるということも。
📔『漢字と日本人』/高島俊男/文春新書
★★★★★
非常にわかりやすく例をひいて漢字と日本人の歴史を書いている良書。Kindleunlimitedで読んだが購入候補。高島氏も日本語の改革に関しては絶望的な立場なんだなあ。日本語がもう造語能力を失ってるというのはよく聞く話で、意味もわかるんだけど、その原因が「抽象的な事も言える言語として発展する前に大量の漢語を入れてしまったから」というのは、認めがたいが、やはり事実。「言語に優劣はない」という左派の考え方を脅かすものだからね。
現代社会で使用されている以上、どの言語も「おなじようなこと」が言えるはずだけど、その中における外来語依存度とか、外国人にとっての習得容易度だとか、やっぱり違うのよな。基準を設けることはできないけど、この点においてこの言語は優れている/劣っている、というのは確実にあります。
以下徒然
・「呉音」というの、今までベトナム人学生に「三国志の呉から伝わったのだ」とか適当に教えてましたが、厳密には「六朝時代の中国南部から徐々に、長い時間をかけてコマ切れに入ってきた発音」なんだなあ。
・漢語の読みが時代によって違うというのも知らなかった。「戦国時代にタイムスリップしたら、当時は孔子をコウシではなくクジと読んでいたので話が通じない」。うーん、無教養な人と思われてしまう。
・「権利だの社会だの共和だのといった語が古の漢籍にあると言っても、それでも明治の日本人が発明したというのも事実」。うむ、右翼は馬鹿だが、左翼も行き過ぎだよな。
フィクション(4冊)
📔『准教授高槻彰良の推察 ex3』/澤村御影/角川文庫
★★★☆☆
このシリーズも長いなあ。早く決着しないかしらん。
📔『みかんとひよどり』/近藤史恵/角川文庫
★★★★★
近藤史恵さんは随分昔に自転車レースモノの2作品しか読んだことなかったけど、こんな感じの優しい物語を書く人なんですね。あと数作読んでみようと思います。
📔『鹿男あをによし』万城目学/幻冬舎文庫
★★★☆☆
森見登美彦は読んでいたが、同じ「関西マジック・リアリズム」の作品とされるこれは今まで読む機会がなかった。それなりに面白かったが、読後に残るものは何もなかった。エンターテイメントでマジック・リアリズムって結局は読者を煙に巻く話にしかならないのかなあ。前フリで書かれた主人公の「神経質さ」「助手との確執」が消化されないまま終わっているのも残念。
📔『不動清の心霊物件ファイル』/あかつき陽/大都社・秋水社
★★☆☆☆
ひまつぶしに怪談でもと読んでみましたが、全然怖くない自分に気が付きました。調べてみると「大人になって怪談がこわくなくなった」という人は結構いますね。この「大人になって」の基準はいろいろあるでしょうが、私の場合は「自分の子供ができてから怪談が怖くなくなった」という感じがします。
まんが(9冊)
📔『ネムルバカ』『探偵奇譚』『響子と父さん』『ポジティブ先生』/石黒正和
★★★★☆
KindleUnlimitedに出ていたのでざっと読み。
📔『召喚獣士の学校1~3』 /秦和生/DENSHO
★★★★☆
KindleUnlimitedで読んだが買ってもいいかも。この人の絵はかわいらしいしきれいだし、「楚漢列伝αMETEO」のころから気になっていました。あと「謎のファンタジー用語」が急にでてこないところがいい。私なんかは「ドラクエ」とか履修していないもんだから、何の説明もなくドワーフだエルフだという語が出てくると非常に興が削がれます。角川が必死で売ろうとしていた「葬送のフリーレーン」が読めなかったのもこれが原因。本作では「ドラゴン」すら普通に「竜」と呼んでおり、非常に好感がもてます。
📔『新九郎奔る! 19巻』 /ゆうきまさみ/ビッグコミックス
★★★★★
ついに堀越公方家で足利茶々丸のクーデターが起き、そろそろこの漫画も終わりに向かうことになるのか。WEB掲載の連載のほうでは明応の政変が完全に終わった所。しかしここまで描写範囲を広げてしまうと、「早雲庵宗瑞の伊豆討ち入り」を話の終わりにするのはなんか物足りなくなってきてしまったなあ。このあとの細川家内訌、2分裂した足利将軍家(義材 vs 義澄)の勢力争い、扇谷上杉定正の死まで見たくなってしまう。まさかのパート2があったりして。あいや、考えてみれば息子の氏綱も仮名は「新九郎」だからそのまま話を続けてもおかしくないのか。
調べてみると、「イン・メディアス・レス」という技法があるようですね。時系列でA→B→Cと進む話を、B→A→B→Cと語る手法。
📔『創世のタイガ 13巻』/森亘二/白泉社
★★★★☆
相変わらずご都合主義だよなー。どうやって「ナイル川」だと確信しているのか。まぁ面白いけど。刊行ペースが落ちてるのは作者がベルセルクに関わっているからかしらん。