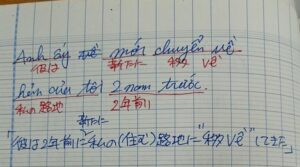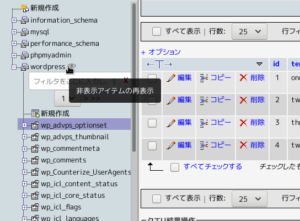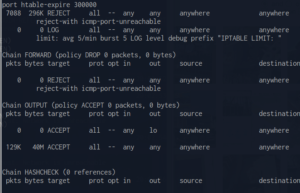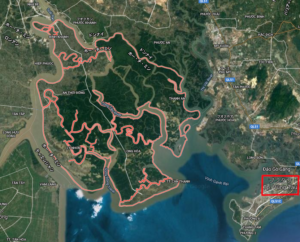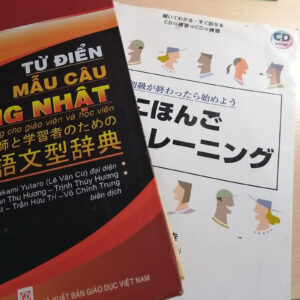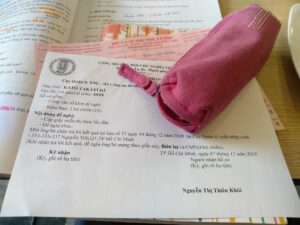8月の読書記録
8月はノンフィクション6冊、フィクション6冊で合計12冊。まんが12冊を加えて24冊。
ノンフィクション(6冊)
📔『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』/古野貢/朝日新書
★★★☆☆
細川政元とあれば買わないわけにはいかない、と前評判の悪さを無視して購入。うーん、1時間程度ですっと読めてしまった。内容薄いです。あと編集者が見落としたであろうミスがぽつぽつ。
📔『日本はなぜ敗れるのか―敗因21ヵ条』/山本七平/角川oneテーマ21
★★★★★
本書は、太平洋戦争に駆り出された技術者が、捕虜生活をもとに描き出した「虜人日記」(小松真一)の解説本のようなもの。存在意義がちょっと?な本ではあるが、やはり山本七平は面白い。この「虜人日記」には日本が破れた「敗因十二ヶ条」というのがある。従来言われてきた物量が云々というのも、もちろんそこに入っているのだが、特に印象深かったのは以下の3条
1.精兵主義の軍隊に精兵がいなかった。精兵でしかできない作戦ばかりやろうとした。
これはあれですね、「百発百中の砲1門、百発1中の砲100門に勝る」という例の勘違い。その上、実際には「百発百中の砲」なんてなかったということ。米国は誰でもできる作戦を立てたが、日本はスーパーマンにしかこなせない作戦を平気で立てた。
15.バアーシー海峡の損害と、戦意喪失
「バシー海峡の悲劇」などと呼ばれている事件。これは知らなかった。戦争後期、日本軍は攻め上ってくる米軍とのフィリピンでの大決戦を夢想し、武器もないフィリピンに、「員数合わせ」のために兵隊を送り込み続けた。しかも台湾~フィリピンを隔てるバシー海峡の制海権・制空権を失っていたのに、そこにただただボロ船を送り続けた。その結果、最大で20万人がここに沈んだとも言われている。日本軍の総死者数は320万人というが、うち5割が餓死だとして、残り160万人のうちなんと12.5%がここで「(愚かな司令部に)殺された」ことになる。またこういう行為が戦意喪失を招き、「日本軍はあまりにも人命を粗末にするので、最終的に兵隊は、上の言うことを聞いたら死ぬ、と理解してしまった」とのこと。「この人について行ったら生き残れるかもしれない」と部下に思わせる(正確には「勘違いさせる」んですけどね)のが優秀な指揮官だと言うが、日本軍は全く逆だったわけである。
21.指導者に生物学的常識がなかった事
「腹が減っては戦はできぬ」。そういった純生物学的な常識がなかったという話。
他にもマーカーを引いた部分が多数。太平洋戦争に関しては、日本人が知らない、知らされていない事がまだまだたくさんある。語っても語り尽くせない事を改めて理解した。やはり「知ったつもり」になって歴史を思い出すことをやめてはいけない。
📔『イスラエル 人類史上もっともやっかいな問題』/ダニエル・ソカッチ/NHK出版
★★★★★
かなり分厚い本ですが、後半の1割以上が出典や注釈や日本語版解説なので、読むのにそこまで大変ではありませんでした。新たな知見として以下のようなものがありました
ベン・グリオンの三角形
「六日間戦争」の直後、イスラエルは以下の3つを持っていた
1.イスラエルはユダヤ人国家である
2.イスラエルは民主主義国家である
3.イスラエルは戦争で多くの領土を得た
しかし、領土を維持しつつ民主主義国家たらんとすれば占領地のパレスチナ人の人権を認めなければならない、パレスチナ人の人権を認めればユダヤ人国家ではなくなってしまう。つまり、領土はすぐに返還するしかないとベン・グリオン(当時もう実権を後進に譲っていた建国の父)は主張したが、これが通ることはなかった。そして3つすべてを維持するために、パレスチナ人に対して最悪の態度をとることになった。
ディスペンセーション主義
もとはといえば、矛盾の多い聖書を「100%正しい神の言葉」であるとするために、「旧約の時代はあの教えが正しかったのだ」「イエス存命中はあの教えがただしかったのだ」と時代に分けてものを考える主張だったらしい。それがいつしか、「聖書の通りに時代は進む」→「『最後の審判』は比喩ではなく、歴史的事件として起きる」という主張に繋がり、また「イエスが再臨して最後の審判が起こるには、聖書の預言書どおりの事が起きなければならない」→「ユダヤ人がパレスチナに国家を作ることがそのステップの一つである」という妄想になってしまった。そしてアメリカの福音派の多くがこれを信じているために、アメリカはイスラエルを支持してしまう……というなんとも4文字言葉な主義である。当然福音派ではないプロテスタント諸派やカトリックはこんなことを信じてはいない。
📔『日本の植民地支配 肯定・賛美論を検証する』/岩波ブックレット
★★☆☆☆
しまった。ブックレットだ。お金払って買ってしまったが薄ーい。84ページしかない。しかも内容は非常に観念的・情緒的で、きちんと数字をあげての検証が少なすぎる。左派で反大日本帝国の私からみても無理のある論証が目立った。たとえば「日本の建設したインフラは現地のために全く貢献しなかった」みたいなデタラメも描かれている。いや、インフラを作ってそこに残した以上、何らかの役にはたってるでしょ? 役に立てる目的じゃなかったとしても立っちゃってるわけじゃん。インフラに関して大日本帝国を否定するのであれば「大日本帝国は現地に学校や鉄道を構築したから欧米よりいい支配だったのか」という題のを立てて、「いや、イギリスやフランスのほうがもっと熱心にやりましたけど?」と返すべきである。「ナチスはいいこともしたのか?」に比べたらまったく薄っぺらい内容でした。
📔『ドイツ人のすごい働き方』/徳留慶太郎/すばる舎
★★★☆☆
たまにはこんな本も。ベトナムは定時はしっかり守るけどやはりアジアなので働き方は結構ダメなんだよな。欧米のような休暇がほしい。
📔『ほんまにオレはアホやろか』/水木しげる/講談社文庫
★★★★☆
水木氏の戦争中の自伝。戦争中を扱ったものは以前に漫画で読んでいるが、これは幼い頃から戦争中、漫画家として名が売れるまでを書いたもの。最後はニューギニア再訪の話で終わっていてあれ?と思ったが、なるほど、これは1978年に書かれたものなのか。
フィクション(6冊)
📔『そして、ユリコは一人になった』/貴戸湊太 / 宝島社文庫
★☆☆☆☆
学園サイコミステリもの? 文章もプロットも下手くそ。登場人物のリアリティゼロ。セリフ回しも40年前の学生演劇みたい。読むのにかなりの忍耐を強いられました。「このミス」でテレビドラマ化を前提にした特別賞をとったそうな。先月読んだ同じような趣向の作品 『教室がひとりになるまで』/浅倉秋成/角川文庫 がいかに上手に書かれていたかよくわかります。
📔『覇道の槍』/天野純希 /角川春樹事務所
★★★★★
三好元長をメインの主人公に据え、足利義維(堺公方)、細川六郎晴元、そして元長に拾われて忍として鍛えられた孤児の少年を中心に語られる歴史小説、いわゆる「両細川の乱」「堺公方」を描いている。歴史的事件で言うと等持院の戦いから、三好長慶の上京前夜まであたり。この時代は足利将軍家、管領たる細川京兆家、この後に政権をとる三好家がそれぞれ分列合従を繰り返し、また力をつけた国人たち(柳本、木沢、浦上、浅倉、茨木……)などもそこに絡んで、さらに足利将軍家などは改名しまくるし、みんな偏諱を賜ったり通字を受け継いだりしているので同じような名前がどっさり。はっきり言って「応仁の乱」よりはるかに分かりづらい時代だが、そこをうまく整理して書かれており読みやすかった。こうやって「物語」を読むことでキャラクターイメージを蓄積していって、いつかこの時代の通史をきちんと読みたいものである。
1月に読んだ 『足利将軍たちの戦国乱世 ──応仁の乱後、七代の奮闘』/山田康弘/中公新書 も読みなおそう。あと2月から積読の 『三好一族 戦国最初の「天下人」』 天野忠幸(中公新書) も読めたら良いなあ。
📔『乱都』/天野純希/文春文庫
★★★★★
上と同じ作者の室町もの(2023年購入)を再読。畠山義就、細川政元、大内義興、細川高国、足利義輝などを主人公に「京の都」の魔力を描く連作短編集。『覇道の槍』を読んでからだと、前回読んだ際にはわからなかった物語の背景や歴史の中の位置づけがよくわかってよろしい。
📔『毒』/深谷忠記/徳間文庫
★★★★☆
結構古い作品。作者はトラベルミステリーで有名な人らしいが、本作はドメスティックバイオレンスにからんだ2件の毒殺・毒死事件を描いた正統派ミステリー。ひさしぶりにこういうの読みました。トラベルミステリーも読んでみたいですね。そういうのもう30年くらい読んでいないのでたまには。
📔『殺人者 – ソウル・マーダー』/深谷忠記/徳間文庫
★★★★☆
タイトルの「ソウル・マーダー」というところから、感のいい読者は「レイプ被害者/虐待被害者」を思い浮かべると思うが、その種明かしを作中のどのあたりですればいいのか、というのを考えながら読んでしまった。タイトルの種明かしを最後のオチに持ってくるのって、途中で気づいた読者にはすんごい肩透かしになりますよね。どのへんで明かすのがいいのか、そしてオチはどうもっていけばいいのかという作品構造について考えた。また本作では「犯人と思しき人間のモノローグ」が途中に何度も織り込まれていて、この手法についてもあれこれ考えながら読んだ。いやサスペンスミステリとして十分面白かったですが。
📔『いつかの人質』/芹沢央/角川文庫
★★★★☆
幼い頃偶発的に誘拐されてしまい、不幸な事故から失明してしまった少女。その少女が中学生になったとき、また誘拐された……というサスペンスミステリ。アイデアはめっちゃいいのだが、いまいちリアリティに欠ける部分がちらほら。またあまり派手なシーンもないので、単発の作品としてはパンチが弱い。探偵役が主人公のシリーズものの中の1冊だったらこの惜しさは感じられなかったのではないかと思う。たとえば森博嗣の「Vシリーズ」の一話だったら、みたいな。でも面白かった。
まんが(12冊)
📔『半分姉妹』/ 藤見よいこ/ トーチコミックス
★★★★☆
日本に住む、いわゆる「ハーフ」(ダブルルーツ)の人々を主人公にした連作。電書が紙書籍と同時発売じゃなかったので電書はでないのかなーと思っていたら出ていた。移民1世の私としては彼/彼女らの父母が気になります。
📔『五佰年BOX』3~4.5/宮尾行巳/イブニングコミックス
★★★★★
先月の続き。打ち切りだったか。惜しい。
📔『ベルセルク』43/故・三浦建太郎、スタジオ我画/ヤングアニマルコミックス
★★★★☆
ストーリーの展開が遅いなあ。いつ完結するんだろう。
📔『よそじの新婚メシ事情』1~3、『よそじとふたごのメシ事情』、『モノローグ書店街』、『わびれもの』、『これでおわりです』/小坂俊史/バンブーコミックス
★★★★☆
おお、この作家知らなかった。竹書房系の4コマメインの作家ですね。可愛らしい絵で結構面白いものを書く。ひまつぶしにちょうどいいですね。
年間累計
| 月 | ノンフィクション | フィクション | 非まんが合計 | まんが | 月の総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8 | 15 | 23 | 12 | 35 |
| 2月 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 |
| 3月 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| 4月 | 9 | 5 | 14 | 3 | 17 |
| 5月 | 9 | 10 | 19 | 7 | 26 |
| 6月 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 |
| 7月 | 7 | 9 | 16 | 14 | 30 |
| 8月 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 累計 | 55 | 58 | 113 | 64 | 177 |